こんにちは。ぽこぱぱです。今回は口唇口蓋裂の子供への「言葉の治療」について、参考書籍を読み勉強をします。板書のように記事を書いております。
言葉の治療
口唇裂・口蓋裂の手術のあと、幼児期になってもなかなか言葉がはっきりしないことがあるそうです。言葉の遅れが出たとしても、適切な治療や発音の練習をすることで発音を改善できるといいます。
どうしてうまく話せないのか?
口蓋裂の手術を適切な時期に行なっても、幼児期以降も言葉の不明瞭さが残る場合は、鼻咽腔閉鎖機能不全(びいんくへいさきのうふぜん)や、構音障害(発音の誤りの固定)の可能性があるということです。
鼻咽腔閉鎖機能不全とは?
私たちが話したり、食べ物を飲み込んだりする時、息や飲食物が鼻から漏れることはありません。
この漏れないようにしてくれる機能を、鼻咽腔閉鎖機能と呼びます。
口蓋裂があっても1歳ごろに行う手術で、この機能を獲得できるそうです。
この鼻咽腔閉鎖機能が良好でない状態の事を鼻咽腔閉鎖機能不全と呼びます。声が鼻に抜けたり、口から吹く力が弱くなったりするといいます。
こういった場合は病院で検査や治療が必要だと言う事です。
発声と発音の発達
発生と発音は一般的に、生まれてから小学校入学の頃までに次第に発達していくといいます。
発達の経過は以下の通りです。
- 0か月…泣くという発声
- 2〜3か月…「うー」など泣かずに声を出す
- 5〜6か月…人や物に向かって声を出す
- 6〜8か月…「マママ」など「あーうー」意外を発音
- 1歳頃…「ママ」など意味と結びつく
- 3歳頃…年齢と共に言葉の数が増える
- 6歳頃…発音がほぼ完成
口蓋裂の場合は?
口蓋裂がある場合、手術前は発音ができる音の種類が限られる事が多いそうです。
手術後、音の種類が増えていきますが、一部の音で発音の誤りが固定されてしまう事があるといいます。
例えば…
●声門を強く閉めながら、のどを詰めたような発音「声門破裂音」 例)「コップ」→「オッウ」
●舌の前の方を使う音が、後ろへ移動する「口蓋化構音」 例)「タ」→「カ」に、「サ」→「ヒャ」「シャ」に近い音になるそうです
これが構音障害(こうおんしょうがい)です。多くの治療機関で、口蓋裂の手術後に構音障害があったお子さんは、全体の30%〜40%であったという報告もあるそうです。
それでも、適切な時期に訓練を受けたり、治療を受ける事で改善し、明瞭に話ができるようになるということです。
発音の訓練
言葉の発達に大切なこと
「おしゃべり」をするためには、「わかる」ことや、「伝えたい気持ち」がとても大切です。この3つがバランスよく育つことが『言葉』の発達だそうです。
「おしゃべり」や言葉を「わかる」ためには、「運動機能」や「口の働き(口腔機能)」、「聴く」「見る」「情報を理解する」「記憶する」「身振りや声のマネ」など様々な力が必要です。
また、たくさんの「愛情」を受けた赤ちゃんと両親の間には絆が生まれて、「伝えたい気持ち」が高まります。
心と体の健やかな成長が『言葉』全体を育んでいくと言う事です。

発音の訓練の進め方
以下の場合には発音の訓練が必要だといいます。
- 口蓋裂に関連する発音の誤りが固定化し、改善が困難
- 発音が不明瞭で伝わりにくい
- 本人が正しく発音できず気にして話したがらない
こういった場合には、病院や各自治体の療育期間、小学校の言葉教室などで受けることができるそうです。治療を受けている医療機関の「言語聴覚士」と相談して通いやすい訓練先を探すということです。
【言語聴覚士】(げんごちょうかくし)
「言語聴覚士法」にもとづく国家資格。言語訓練などについて、必要な検査や助言、指導、その他の援助を行なってくれます。
乳幼児期から3〜6か月ごとに言語理解やコミュニケーション能力なども含めた「言葉」全体の評価をしてくれる。
発音の訓練の進め方は以下の通りです。
- 開始時期:4〜5歳頃
- 訓練方法:お子さんそれぞれに対し言語聴覚士が指導
- 1回あたりの訓練時間:30〜40分程度
- 訓練頻度:原則週に1回
発音の訓練はいつから?
訓練は4〜5歳以降に開始することが多いそうですが、幼児期からご家庭でできる事もあるそうです。楽しく声をだして遊んだり、唇や舌を動かすことは大切だということです。
0から1歳ごろまで
- 積極的に声を出して遊ぶ
- 1歳前には身振りや音マネを始める
- パパ、ママのの口元を観察してます
- 遊びの中で声をたくさん出す
- やりとりの楽しさを経験させる
口蓋裂の手術から2歳ごろまで
口蓋裂の手術から1〜2か月経過後
- ラッパや笛などを吹く
- スプーンやレンゲに水分を入れすする
- 短く切った麺をすする
- ストローで飲み物を飲む
- パ行やバ行出せるように音マネ遊び
2歳以降
言葉の言い直しはさせず正しい言葉を聞かせる
2歳以降、おしゃべりは増えますが、大人と同じように発音できない事も多い時期です。このような時は言い直しをさせず、やりとり中で正しい音を聞かせてあげるのが良いそうです。
正しい音を繰り返して聞く事で、発音もはっきりしてくるそうです。
唇や舌をよく動かす
鏡を見たり、まねを楽しんだりしながら唇や舌の動きを体験させてあげるといいそうです。
- 舐める動作
- チューの仕草
- コップでガラガラうがい
- あっぷっぷで頬を膨らませる
4〜5歳
発音の訓練に加えて、「正しい音」と、「誤った音」を聞き分ける力を育てるための耳の訓練や、舌の運動訓練、音への意識を高める訓練なども並行して行うそうです。
ぱ行の「ぷ」の訓練
- 呼気を頬にためて唇で止めて、一気に開放
- ①の後に「う」をつけて「ぷ」にしてみる
- 「ぷ」の前後に「あいうえお」をつける「あぷ」「ぷえ」など
- 「ぷ」のつく単語を発声
- 「ぷ」の単語を用いた文をしゃべる
- 「ぷ」が入った文で設定をつくり会話
聴覚弁別訓練
カード2枚を提示して、言語聴覚士が単語の名前を言って、子供が正しい方を発音して選択する。
舌を動かす練習(舌運動訓練)
舌を左右口角に接触させたり、上の歯茎につけたりする。
音や文字の意識を高める訓練
こどもに「たいこ」の絵を見せて、その単語は「いくつの音でできている言葉」か、「初めの音は何か」を言語聴覚士が尋ねる。
「たいこ」の場合は…「た・い・こ」の3つの言葉でできていて、初めの音は「た」。
まとめ
はい。という事で、口蓋裂の言葉の治療について勉強しました。
私自身もまだまだ勉強中です。まだ実体験がともなっていません!
でも知らないより、今のうち知っておいた方がいいに決まってます。
今後ぽこちゃんが生まれた時には、そのリアルな実体験を改めてブログに書かせていただきます!
自分の勉強のため、その知識を共有して皆さんのお力になれれば嬉しいです。ではまた。
##
今回の記事は↓を参考に表現を噛み砕いてに書いています。
【メディカ出版】患者説明にそのまま使える不安なパパ・ママにイラストでやさしく解説こどもの口唇裂・口蓋裂の治療とケア(大久保文雄編著)

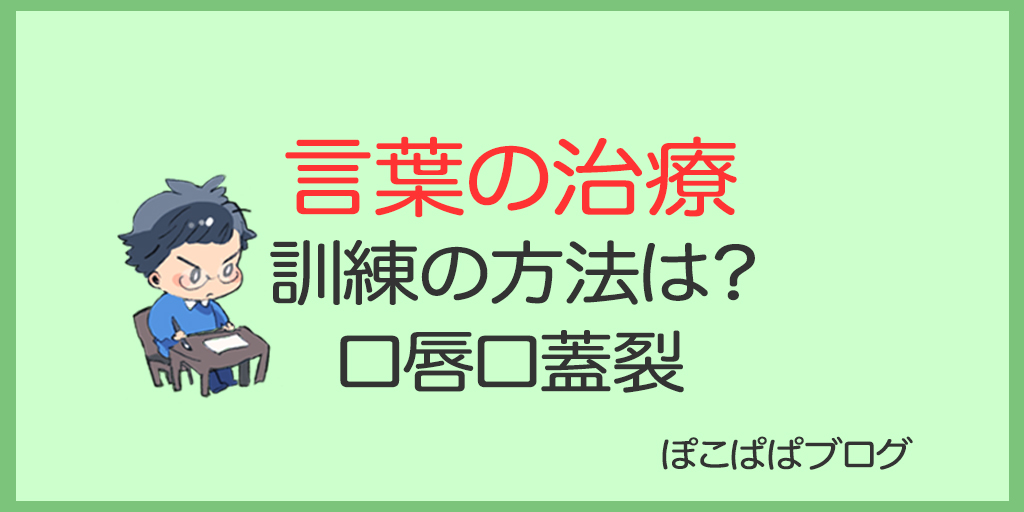


コメント