こんにちは。ぽこぱぱです。
今回もスティーブン・R・コヴィー氏の著書「7つの習慣」をわかりやすく噛み砕いた版の本
「13歳から分かる!7つの習慣 自分を変えるレッスン」を読んで大事なポイントを抽出します。
この記事では7つの習慣のうちの第1の習慣「主体的である」をまとめていきます。
この記事は、「人生が何か上手くいかないなあ…」という方に読んで欲しいです。日々、忙殺されて麻痺した心が少し楽になるかもしれません。

自分の人生を取り戻す第一歩として、まずは自分の心から取り返してみてください。
主体的な行動をする
一時停止ボタンを押して考える
まず主体的な行動とは「自分の意思を持って行動する事」と、この本ではされています。
何かが起きた時にとっさに行動をするのではなく、一度立ち止まって考えてみるという事です。
反応的な行動と主体的な行動
行動の仕方には2つのパターンがあります。
①反応的な行動
<刺激>→<行動>
②主体的な行動
<刺激>→一時停止→<行動>
①の「反応的な行動」は、刺激(何かが起こった)時に何も考えず行動している事です。
簡単に言えばツイッター見てる時に何も考えずに「いいね」押す行為ですね。
②の「主体的な行動」は刺激を受けたあとに、心の中で一時停止ボタンを押しています。
この一時停止ボタンを押している間に「どう行動するべきか」を考える事で主体的な行動を選ぶ事ができます。
例えば、友人のが芸能人の誹謗中傷のツイートをリツートしていた時…。自分はそれに「いいね」をするべきか考える事ですね。少なくとも負の拡散を担わなくてすみましたね。ひょっとすると「そういう事はよくないよ。」と注意することもできるかもしれません。

“全てを我慢をしろ!”というわけじゃないよ。
もう一つの例です。何か欲しい物をみつけた時に、「衝動的に買う」のか、一度「本当に必要なのか納得した上で買う」のかでは結果が同じでも、全然意味が違います。
衝動的に買うというのは自分の意思が介入していないので「買わされた」に近いのです。こんな事をしてたら自分の人生が振り回されます。
友人からいらない健康食品を買わされたり、必要のない余計な保険のオプションをつけてしまうかもしれません。(自戒の念を込めて…。)
それが主体的に行動すればそういった無駄を排除できるかもしれません。
影響の輪を意識する
そして、主体的な行動をするためにはもう一つの方法があります。それは影響の輪を意識すること。
実は主体的にできる事というのは限られています、その限られた事を「影響の輪」といいます。逆に興味はあるけど自分ではどうしようもできない事を「関心の輪」といいます。
「影響の輪」とは「関心の輪」
図にするとこんな感じです↓
【関心の輪】
●過去の失敗 ●人からの評価 ●うわさ話 など
※自分では変えられない事
【影響の輪】
●今日やること ●学校の成績 ●人間関係 など
※自分で変えられる事
関心の輪の中にある事は、自分では変えられないのでエネルギーをそこに注ぐのは無駄になってしまいます。なので、限りあるエネルギー(活力や時間など)は影響の輪の中の事に注いだ方が効率的だという事です。
つまり、自分を主体的にするためには、自分で変えられる物事に集中して、影響の輪を広げていく事が重要となりそうです。

「関心の輪」を追いかけて消耗しないように!
ちなみに関心の輪の最たる例はワイドショーのゴシップとかでしょうか。芸能人の恋愛事情に関心があるかもしれませんが、自分がどうあがいても影響を与える事ができませんよね。そんなのを見てる暇があるなら本読め・勉強しろ・ブログ書けという事です。
自分との約束を守る
そして第1の習慣を自分のものにするのに重要な事は「自分との約束を守る」という事です。
これは「早起きする」とか、「あいさつをする」とかでいいそうです。この些細なことを実行して、継続する事が大切。
自分との約束を守り続ける事で「自分は責任を果たす人間だ」と感じ、「主体的である人間」なるための土台となるようです。
さらに、この「主体的」であるという第1の習慣こそが、第2、第3…と続く習慣の基礎になります。
まおめ
はいという事で、7つの習慣のうち、第1の習慣「主体的である」をお伝えしました。
文字で書くのは簡単ですが、結構キツい人にはキツいよね…。というのが私の感想です。
どうしても人の意見に流されてしまいますし、嫌な事があったら一時停止ボタンを押す前に反応してしまいそうです。
でも、ちょっとずつでもいいので、自分を変えてみようと思います。
なぜなら自分を変える事は「影響の輪」の中にある事なので。会社や他人に振り回されるのではなく、自分で考えて未来を築いていきたいものです。
次回は第2の習慣「終わりを思い描くことから始める」です。
ではまた。

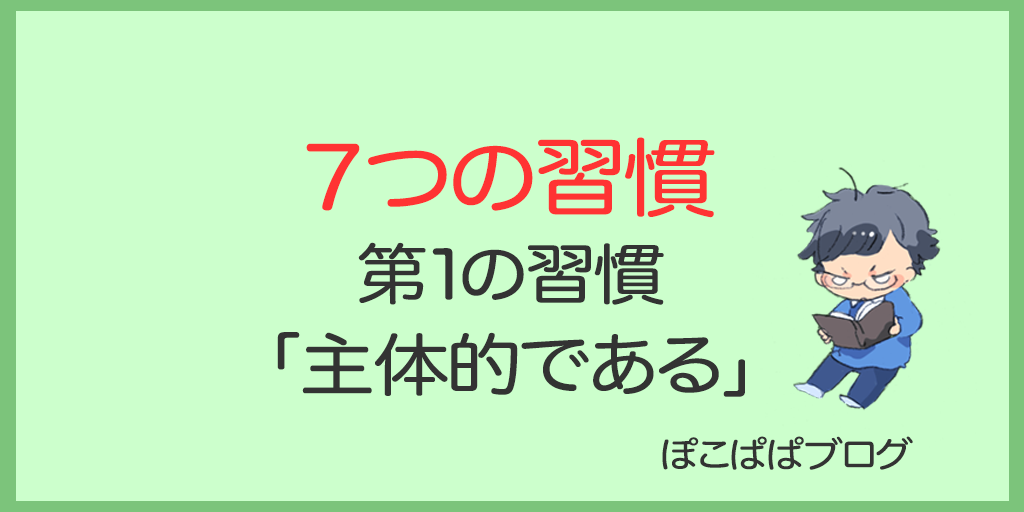
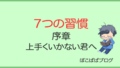

コメント