こんにちは。ぽこぱぱです。
今回は「超訳資本論 お金を知れば人生が変わる」(許成準・著/彩図社)をご紹介します。
この本は歴史の教科書にものってる経済学者マルクスの「資本論」を現代の話に落とし込み、噛み砕いてわかりやすく解説してくれます。
この本を読んだ私の感想は…
- アレ…お金って結構簡単に増やせるんじゃ。
- うわ、私達って会社に搾取されてるわあ。
- 上司達も搾取される側なのか…
と、会社員でいることに疑問をもってしまいました。
ある意味で新鮮な気付きを与えてくれます。
では本題です
ぽこぱぱ的に、この本の大事なポイントをぐぐっと3つに絞り込みました。
- そもそも資本とは
- 労働力とは労働者が売る資本である
- ひとはなぜ金持ちになれないのか
それでは見ていきましょう。
①そもそも資本とは
現代の日本は、資本主義です。でも、そもそもこの「資本」って言葉をよくわかっていない人も多いと思います。
この本では、資本を「お金を稼ぐお金」の事と定義しています。
労働によってお金を稼ぐのではなく、お金に働いてもらうのです。
机上の空論と思えるかもしれませんが、仕組みはいたってシンプルです。
これを見た時に私は「アレ…お金って結構簡単に増やせるんじゃ。」と思ってしまいました。
その考え方はこちら。
「普通の考え方」と「お金の増える考え方」を対比。
【普通の考え方】商品→お金→商品
【お金の増える考え方】お金→商品→お金
「なんだ、ただ順番を入れ替えてるだじゃん。」って思いました?でも冷静に考えるとこれこそが真理だという事がわかります。
一つずつ見てみましょう。
これは、商品を売ってお金を得て、そのお金で商品を購入することを指します。
商品を売るというのは、「労働をして賃金を得る」に置き換えても大丈夫です。いわば得た給料で、ご飯を買って、家賃を払って、携帯の代金を支払うということ。あとはちょっと遊びに使ってしまったり…など。
みなさんの経験では、その結果どうなりました?手元にはほとんど残りませんよね。
ではもう一つの例を見てみましょう。
これはお金で商品を買って、その商品を買った時より高い値段で売って、最初より多いお金を得ることです。
ではこの得たお金をもとに次の商品を買って…とサイクルを回していくと…。おや!おや!おや!どんどんお金が増えていくではないか!
と、こんな感じです。このように流通してくお金の事を「資本」というようです。
ここで注意が必要なのは、「転売をしろ!」と言ってるわけではありません。こういう考え方でお金が増えているんだよと言ってるだけです。
「そんな上手くいくものかな?」と思うかもしれません。
でも、会社員の私たちは忘れがちですが、よーく考えれば、世の中のお店などは全部この仕組みで動いています。
【農家の場合】 ・お金→苗や種を買う→育ったら売る→次の苗を買う 【卸しの場合】 ・お金→生産者から仕入れる→スーパーに売る→仕入れる 【スーパーの場合】 ・お金→商品を仕入れる→客に売る→次の商品を仕入れる 【職人の場合】 ・お金→材料を仕入れる→売る→次の材料を仕入れる
実はこれ、小学校とか中学校の社会で習っているんですよね。私たちは忘れているだけ。たぶん当時のノートが残っていて、見返えしてみれば、2〜3行は書かれているんじゃないですかね。
ぽこぱぱ的考察①
じゃあなぜ私たち会社員はこのサイクルが回せないのか?
これは私が本を読んで感じた事ですが、このサイクルの部品にすぎないからです。
サイクルを回すプレイヤーではなく、仕組みの中に組み込まれている部品の一つなのではないかなと思うのです。
詳しくは、次のポイントで述べさせてもらいます。
②労働力とは労働者が売る資本である
労働者=サラリーマンとは何なのか?この本ではこのように表現されています。
豆腐屋は豆腐を売る職業。魚屋は魚を売る職業。 ではサラリーマンは?サラリーマンは労働力を売る職業である。 労働力を商品として売り、 資本家は労働力を買い、それを利用してビジネスを行う。 つまり、労働者がどんなに頑張って成果をあげても その価値は、労働力を買った資本家の物になるということ。
「お金→商品→増えたお金」のネタバラシ
本書の中では、「お金→商品→お金」のサイクルの正体を解き明かしています。
「お金→商品」と「商品→お金」は等価交換なのに、実際は「お金→商品→増えたお金」になる。
つまり、「増えたお金」になるには「商品」が消費される段階で起きているのです。
1000円→10匹の熱帯魚買う→50匹に増える→5000円 こうなります。
これは熱帯魚を50匹に増やすために繁殖させています。
最初に支払った1000円で、“熱帯魚の繁殖能力”も一緒に買っているのです。
このように、自ら価値を生産する事ができる商品を買えば、等価交換のルールの中でも価値を増加できるのです。
ということは…私たち会社員(労働者)は、この例にのっとると、熱帯魚にあたります。
資本家の富の増加は会社員(労働者)が生み出した価値によるものなのです。
ぽこぱぱ的考察②
どうですかね?ゲーマーである私が思ったのは…
自分たち会社員はゲームの登場人物ではあるけど、操作するもの(プレイヤー)ではない。
ゲームの登場人物は敵を倒しゴールドを得ますが、本質的にその所有者はプレイヤーです。
ゲームの主人公がいかにその世界を救ったとしても、それを指示したのはプレイヤーです。
セーブを消したり、ゲームそのものを売られてもゲームの主人公には何もできません。生殺与奪の権はプレイヤー次第です。
わからない人にはとことんわからない例えですみません。
でも実際の世界では、労働者の権利や、人権などもありますから、ここまで極端なことはないと信じたいです。
ホワイトな企業もたくさんあると思います。
でもブラック企業で働いている方には刺さっているかもしれませんね。退社するため、抜け出すための勇気になれたら嬉しいです。
③ひとはなぜ金持ちになれないのか
「真面目に努力すればきっと成功できる」
と、幼い頃に多くの人が教えられた言葉があると思います。
でも大人になるにつれて、それが間違っていたことを悟りはじめます。
なぜならば、この資本主義のシステムの中ではこの教育方法だけでは金持ちになる事ができないからだとこの本は言っています。
結論:労働の結果は資本家のもの
その理由は簡単。労働の結果は資本家のものだからです。
マルクスの「資本論」ではこう書かれています。
労働者が職場に入ってから彼の労働の使用価値は、資本家の所有になる。 資本家の観点からすれば、労働のプロセスはただ彼が買った商品。 労働力と原材料の相互作用にすぎない。
さらにマルクスはこんな表現もしてます。
まるで酵母がブドウを発酵させてワインを作るように、
資本家が買ったもの同士の相互作用で商品は作られる。
そして、それは資本家の所有となる。
うん。きびしいですね。
パックマンの例
この本ではパックマンの例が出されています。
ゲーム史上もっとも成功したアーケードゲームとしてギネス世界記録にもの載っている「パックマン」
このパックマンを開発した人はとても金持ちになっているのであろうと思われがちですが…
実はゲームの売り上げに対する報酬は何ももらっていないというのです。
なぜこんなことが起きるのか?それは被雇用者だからです。つまり会社員だから。
会社員に決まった額を支払うことで、会社は労働力を買っています。
パックマンの開発者を採用する時に、こんな偉業を成す思って結んだ契約をしたわけでもないのも事実。労働と所有は分離されているのです。
ぽこぱぱ的考察③
この例を見たとき私はこう思いました。

私が尊敬している会社の上司のあの人や、この人。
とても優秀だし会社にとても貢献してるなあ…。

でもその成果は全部会社の利益に持ってかれていくのか…。
多少のボーナスはもらっているんだろうけど…。

むしろ、その額ぐらいなら僕の副業の2か月分くらいだなあ…。
どんなに頑張っても、プレイヤーにならないと人生単位では勝てないんだとつくづく考えさせられました。
ここでの言及は避けますが、会社が株式会社だった場合、そもそも会社の利益は株主のものです。
そして、TOPIXに投資してる私は皆さんの頑張りをいただいている側の人間でもあります。
なので、みなさんの周りの上司の方々がどんなに頑張っていても、その頑張りは本人達以上に会社の所有者や、株主が喜ぶ仕組みになっているのです。
もちろん、現代社会ではこの限りではないと思います。
思いますけど、あなたはどう思いました?
まとめ
※これはあくまでも個人の感想です。
私はどうしてもこの本を読んだあとの感想は、なんだかんだ搾取されているなあ。と思いました。
だって、自分がオーナーになって同じ事をしたらそれ以上に稼げるのですもの。
実際に私は副業でYoutubeのお手伝いをやってますが、1日2〜3時間の作業で月給の半分くらいは稼げちゃいますから。ただめちゃくちゃ頑張りました。本業が終わって寝るまでの時間をコツコツ使っての毎日更新ですから。その代わり、報酬としての跳ね返りはとても大きかったです。
もちろん会社員ではないというのにはリスクもあります。
コロナ禍の現状で多くの経営者の方は頭を悩ませいるのも事実ですし、「お金→商品→お金」の段階で商品が売れない事なんて多々ありますからね。
これはメルカリなどのフリマアプリをしてみるとすごく痛感します。1円を稼ぐ難しさを知る事になります。配送料とか手数料でほとんど手元に残らんがな!と。
でも試行錯誤をする事で、どこかでブレイクスルーします。
ブレイクスルーをするには、まず思考を変えないといけません。
パラダイムシフトですね。
思考を変えるにはまずは「知る事」が大事です!
その一方で、フェイク情報も世の中に溢れているので気をつけてください!ではまた!

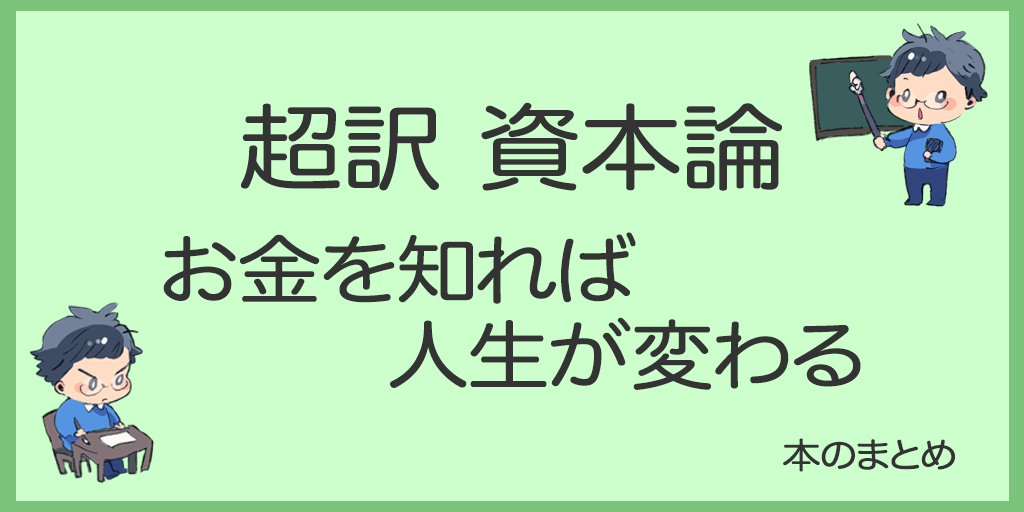

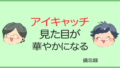
コメント